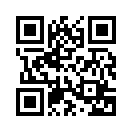2014年12月24日
矛盾を語った時の疑問から
「この世の中は矛盾に満ちている」というような言葉で前回のブログを閉じましたが、日々の暮らしの中に身を置いている私自身が私の世界観で世の中を見る視点とまた私自身の自己矛盾的な存在として日々の思考の中にいのちの彼岸へと向かっている過程のなかで自分を見つめる視点を合わせ持っています。
「矛盾がある」
「矛盾している」
その合わせ持っている視点は、上記のようにそのように吐露するのですが、この「矛盾」を語るとき対比的な感覚で物をとらえていることに気がつきます。
「こうあるべきもの」
が自己理解の判断の心底にあります。表現として心底に写しだされ現われてくるとも言えると思います。
矛盾とは自分の尺度において対極なり相異をそのなかに捉えるのでしょうが、なぜにそのような気が現われるのでしょう。
世の中は、移りゆくもの、そこに「無常」を見るのが日本人の思惟の世界のようですが、そのような情緒感で「矛盾」を考えると、「矛盾がある」という断定よりも、後者の「矛盾している」という「そういうものである」的な、ただその中に「ある」存在に視点を置く方が落ちつくような気がします。
世の中も、自分もその時々の流れの中で、どこまで流れればその矛盾に気がつくのだろうか。
今まさに矛盾を感じるとはどういうことなのか。
「案ずる」
という思い巡らすことは、「未だ来たらず」の想い煩いであって本当に矛盾などというものがあるのだろうか。
概念、意味、論理、説明、理由、理論、思想(ロゴス)
これらが語られるのは、意味による範疇化でしかないのではないか。
「あるものがあるかないか」(事実存在)
「あるものが何であるか」(本質存在)
存在について故木田元先生は語っていましたが、これは上記の
「矛盾がある」
「矛盾している」
は私自身この言葉に重なり感じます。後者の「矛盾している」は本質の理解が無ければ語られないことは自明で、前者は相異があるかないか、「ある」「ない」の決定で「ある」以上それは「ある」に終局します。
「矛盾がある」
と断定した時、矛盾があると語った時、人間は苦悩に陥らざるを得ない。
矛盾とは二元論で語られる対極の只中の間の現れであって、「あるものが何であるか」を言い抜いて、突き破らない限りは、人間は苦悩し続けることになるのではないか。
「現象というものは、Aでもあれば非Aでもある」
それは差異とも呼べそうですが、「現れ」は形成の只中の「ある」にしか表現できません。
ベッカム実存主義が着飾りのメタモルフォーゼに走るのは、どうも回避にすぎないように思えるのです。
心底実存に付き合っていない。ある意味「力の意志」や「回避意志」の存在の忌避上を離れていないように思うのです。ベッカム実存主義はある意味、助けにはならないと思うのです。
「あるものがあるかないか」(事実存在・existentia)
は「現実存在」と哲学者の松浪信三郎先生は訳していますが、「実存」という短縮した言葉になります。
実存を突き破ること、これにはやはり心底実存を見つめ、付き合い、根柢を突き破るが寛容に思えるのです。
ということで、個人的な語りの日記を残します。
egobv
egotir
egoluci
egostart
egoxx
linjiangxiann@gmail.com
linjiangxiann@gmail.com
egoto
egowait
missper
「矛盾がある」
「矛盾している」
その合わせ持っている視点は、上記のようにそのように吐露するのですが、この「矛盾」を語るとき対比的な感覚で物をとらえていることに気がつきます。
「こうあるべきもの」
が自己理解の判断の心底にあります。表現として心底に写しだされ現われてくるとも言えると思います。
矛盾とは自分の尺度において対極なり相異をそのなかに捉えるのでしょうが、なぜにそのような気が現われるのでしょう。
世の中は、移りゆくもの、そこに「無常」を見るのが日本人の思惟の世界のようですが、そのような情緒感で「矛盾」を考えると、「矛盾がある」という断定よりも、後者の「矛盾している」という「そういうものである」的な、ただその中に「ある」存在に視点を置く方が落ちつくような気がします。
世の中も、自分もその時々の流れの中で、どこまで流れればその矛盾に気がつくのだろうか。
今まさに矛盾を感じるとはどういうことなのか。
「案ずる」
という思い巡らすことは、「未だ来たらず」の想い煩いであって本当に矛盾などというものがあるのだろうか。
概念、意味、論理、説明、理由、理論、思想(ロゴス)
これらが語られるのは、意味による範疇化でしかないのではないか。
「あるものがあるかないか」(事実存在)
「あるものが何であるか」(本質存在)
存在について故木田元先生は語っていましたが、これは上記の
「矛盾がある」
「矛盾している」
は私自身この言葉に重なり感じます。後者の「矛盾している」は本質の理解が無ければ語られないことは自明で、前者は相異があるかないか、「ある」「ない」の決定で「ある」以上それは「ある」に終局します。
「矛盾がある」
と断定した時、矛盾があると語った時、人間は苦悩に陥らざるを得ない。
矛盾とは二元論で語られる対極の只中の間の現れであって、「あるものが何であるか」を言い抜いて、突き破らない限りは、人間は苦悩し続けることになるのではないか。
「現象というものは、Aでもあれば非Aでもある」
それは差異とも呼べそうですが、「現れ」は形成の只中の「ある」にしか表現できません。
ベッカム実存主義が着飾りのメタモルフォーゼに走るのは、どうも回避にすぎないように思えるのです。
心底実存に付き合っていない。ある意味「力の意志」や「回避意志」の存在の忌避上を離れていないように思うのです。ベッカム実存主義はある意味、助けにはならないと思うのです。
「あるものがあるかないか」(事実存在・existentia)
は「現実存在」と哲学者の松浪信三郎先生は訳していますが、「実存」という短縮した言葉になります。
実存を突き破ること、これにはやはり心底実存を見つめ、付き合い、根柢を突き破るが寛容に思えるのです。
ということで、個人的な語りの日記を残します。
egobv
egotir
egoluci
egostart
egoxx
linjiangxiann@gmail.com
linjiangxiann@gmail.com
egoto
egowait
missper