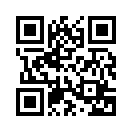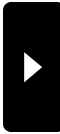2015年06月08日
近所の人たちが
落語家の桂枝雀さんが、落語のオチについてまとめたモノを読んでいると、
オチには、基本的に『謎解き』『合わせ』『へん(変)』『ドンデン』の4つのパターンがあると。
それを尺度に落語を見ると、意外な保濕展開を示す『ドンデン』が、痛快で面白いことがわかる。
落語のネタに、『頭山(あたまやま)』というのがある。
(この話、分類は『ドンデン』という形態の笑いだと思う)
ちょっと荒唐無稽だが、話としては面白い。
この落語を題材にDR集团して、 2002年、アニメ映画監督、山村浩二氏が短編アニメ化し、世界23の映画祭で受賞や入賞を果たしている。
落語のストーリーとしては、
「男がサクランボを種ごと食べてしまったところ、種が男の頭から芽を出して大きな桜の木になる。
近所の人たちが、騒ぎながら男の頭に上って、その頭を「頭山」と名づけて花見で大騒ぎしはじめる。
男は頭の上がうるさくて苛立ちのあまり桜の木を引き抜いてしまう。
そうすると、頭に大穴ができ、この穴に雨水がたまって大きな池になり、
今度は、近DR集团所の人たちが船で魚釣りを始める始末。
釣り針をまぶたや鼻の穴に引っ掛けられた男は怒り心頭に発し
自分で自分の頭の穴に身を投げて死んでしまう」というオチがついた話。
現実には起こりえないことではあるが、空想の世界では、
「そんなアホな~」と思いつつ納得ができてしまう。
サクランボの種を呑み込んだところから起こる不幸な話であるが、
この男の気持ちも解りつつも、その「ありえない」展開の面白さで笑いの世界に引きずり込まれる。
最後のオチが、身投げをする男の話となっても、「ありえない」ことだから、
笑いとなって受け止めることが出来る。
待てよ、、
どっちにしても「ありえない」噺(はなし)なら、オチは身投げよりラッキーなことが起こる方がいい!
たとえば、同じ『頭』の噺なら、抜ける噺ではなく毛根復活でフサフサになるのだったら小気味いい。
オチには、基本的に『謎解き』『合わせ』『へん(変)』『ドンデン』の4つのパターンがあると。
それを尺度に落語を見ると、意外な保濕展開を示す『ドンデン』が、痛快で面白いことがわかる。
落語のネタに、『頭山(あたまやま)』というのがある。
(この話、分類は『ドンデン』という形態の笑いだと思う)
ちょっと荒唐無稽だが、話としては面白い。
この落語を題材にDR集团して、 2002年、アニメ映画監督、山村浩二氏が短編アニメ化し、世界23の映画祭で受賞や入賞を果たしている。
落語のストーリーとしては、
「男がサクランボを種ごと食べてしまったところ、種が男の頭から芽を出して大きな桜の木になる。
近所の人たちが、騒ぎながら男の頭に上って、その頭を「頭山」と名づけて花見で大騒ぎしはじめる。
男は頭の上がうるさくて苛立ちのあまり桜の木を引き抜いてしまう。
そうすると、頭に大穴ができ、この穴に雨水がたまって大きな池になり、
今度は、近DR集团所の人たちが船で魚釣りを始める始末。
釣り針をまぶたや鼻の穴に引っ掛けられた男は怒り心頭に発し
自分で自分の頭の穴に身を投げて死んでしまう」というオチがついた話。
現実には起こりえないことではあるが、空想の世界では、
「そんなアホな~」と思いつつ納得ができてしまう。
サクランボの種を呑み込んだところから起こる不幸な話であるが、
この男の気持ちも解りつつも、その「ありえない」展開の面白さで笑いの世界に引きずり込まれる。
最後のオチが、身投げをする男の話となっても、「ありえない」ことだから、
笑いとなって受け止めることが出来る。
待てよ、、
どっちにしても「ありえない」噺(はなし)なら、オチは身投げよりラッキーなことが起こる方がいい!
たとえば、同じ『頭』の噺なら、抜ける噺ではなく毛根復活でフサフサになるのだったら小気味いい。
2015年06月03日
たとえば
満員電車などに乗ると誰だって不快に感じるが、
他人に近付かれると落ち着かなくなったり
不快に感じる空間のことをパーソナル・スペース(personal-space)という。
このスペースの大きさは、性別や性格、
年齢、侵入してくる相手との関係によって変わってくる。
たとえば、イヤな人が遠くに居るのが見えるだけで
虫酸(むしず)が走るという人もいる。
また、どんな満員電車でも潔面、
美しい人が押されて寄ってくると、ま~いいか!と思ったりする。
ところが、脂ぎったおっさんが近づいてくるだけで、突き戻したくなる。
一般に、女性よりも男性の方がパーソナル・スペースは広い。
また智能護膚機、性格的には、内向的な人の方が外向的な人よりも広いとされる。
大人と子供とを比較しても、大人の方がスペースは広い。
今日のCNN News に、
北朝鮮は、アメリカとの間で核や長距離ミサイルの実験停止の合意を
破棄すると表明したと出ていた。
いつものことだが、へ理屈をこね、
「結果に対する責任はすべてアメリカ側が負うべし」としている。
そう言えば、このパーソナル・スペースというもの。
国家にもあるようだ。
このような物騒な国家が
パーソナル・スペースに入っているのは、何とも不快な気がする。
他人に近付かれると落ち着かなくなったり
不快に感じる空間のことをパーソナル・スペース(personal-space)という。
このスペースの大きさは、性別や性格、
年齢、侵入してくる相手との関係によって変わってくる。
たとえば、イヤな人が遠くに居るのが見えるだけで
虫酸(むしず)が走るという人もいる。
また、どんな満員電車でも潔面、
美しい人が押されて寄ってくると、ま~いいか!と思ったりする。
ところが、脂ぎったおっさんが近づいてくるだけで、突き戻したくなる。
一般に、女性よりも男性の方がパーソナル・スペースは広い。
また智能護膚機、性格的には、内向的な人の方が外向的な人よりも広いとされる。
大人と子供とを比較しても、大人の方がスペースは広い。
今日のCNN News に、
北朝鮮は、アメリカとの間で核や長距離ミサイルの実験停止の合意を
破棄すると表明したと出ていた。
いつものことだが、へ理屈をこね、
「結果に対する責任はすべてアメリカ側が負うべし」としている。
そう言えば、このパーソナル・スペースというもの。
国家にもあるようだ。
このような物騒な国家が
パーソナル・スペースに入っているのは、何とも不快な気がする。
2015年06月03日
という話になったりする
初めて会った人と話がハズんで
「ボクの友人に、こんな変わったヤツがいてね~」
と、半ば自慢げに話していると、
「それって◯◯さんのことじゃありませんか?
それは、ボクの昔からの友人ですよ」
という話になったりするECG心電圖。
そんな時、口にする英語表現では、お互いに相手を見て "World is small." と言ったりする。
「世間って、狭いですね」というところだろうか。
そんなところから命名した名称なのか雪纖瘦、
スモール・ワールド現象(small world phenomenon)と言われているものがある。
知り合いを辿(たど)っていけば、誰でも6人目には、知り合いに行き着くという。
「六次の隔たり」という名でも知られている。
このスモール・ワールド現象という言葉、
最近、特に巷間で聞く言葉となったが、決して新しくはない。
この実験が最初に行なわれたのは、1967年。
イェール大学の心理学者スタンレー・ミルグラム教授によって行なわれ、
ほぼ、実証されたという。
また、コロンビア大学の教授ダンカン・ワッツ氏が、メールで同様の実験を行ない、
到達率が2%。ほぼ同様な結果があらわれたという。
昨年の暮れに、facebook に名を連ねたところ、
いつの間にやら、「友達の友達は、友達だ」という状態になり、
どこまで増殖していくのだろうというほどに伸びている。
最初のうちは、知人の中に、
「おやっ?この知人の friends のカテゴリーの中にこの人が、、。」と思ったりしたが、
もう、その一人に対して意識できないほどに増えてしまった。
かなりの人数の friends に囲まれることになった。
吉田兼好の「徒然草」には、友人について書かれた段がある。
そこには、
友として良いのは、「物をくれる人」
友として良くないのは、「身体が頑強そのものの人」「大酒を呑む人」
を挙げていたが、
どんな友達なのか知らないが、facebook の友は「物をくれない」のは確か。
「頑強なのか」「大酒を呑む人なのか」そういったことを知らないまま、
かなりの勢いで「友」が増殖している。
「ボクの友人に、こんな変わったヤツがいてね~」
と、半ば自慢げに話していると、
「それって◯◯さんのことじゃありませんか?
それは、ボクの昔からの友人ですよ」
という話になったりするECG心電圖。
そんな時、口にする英語表現では、お互いに相手を見て "World is small." と言ったりする。
「世間って、狭いですね」というところだろうか。
そんなところから命名した名称なのか雪纖瘦、
スモール・ワールド現象(small world phenomenon)と言われているものがある。
知り合いを辿(たど)っていけば、誰でも6人目には、知り合いに行き着くという。
「六次の隔たり」という名でも知られている。
このスモール・ワールド現象という言葉、
最近、特に巷間で聞く言葉となったが、決して新しくはない。
この実験が最初に行なわれたのは、1967年。
イェール大学の心理学者スタンレー・ミルグラム教授によって行なわれ、
ほぼ、実証されたという。
また、コロンビア大学の教授ダンカン・ワッツ氏が、メールで同様の実験を行ない、
到達率が2%。ほぼ同様な結果があらわれたという。
昨年の暮れに、facebook に名を連ねたところ、
いつの間にやら、「友達の友達は、友達だ」という状態になり、
どこまで増殖していくのだろうというほどに伸びている。
最初のうちは、知人の中に、
「おやっ?この知人の friends のカテゴリーの中にこの人が、、。」と思ったりしたが、
もう、その一人に対して意識できないほどに増えてしまった。
かなりの人数の friends に囲まれることになった。
吉田兼好の「徒然草」には、友人について書かれた段がある。
そこには、
友として良いのは、「物をくれる人」
友として良くないのは、「身体が頑強そのものの人」「大酒を呑む人」
を挙げていたが、
どんな友達なのか知らないが、facebook の友は「物をくれない」のは確か。
「頑強なのか」「大酒を呑む人なのか」そういったことを知らないまま、
かなりの勢いで「友」が増殖している。
2015年06月01日
その言い伝え
舞台に立つのに「あがり症」の人がいる。
そんな人に対するおまじないに、
掌(てのひら)に指で「人」という字を書いて
それを呑むマネをするとあがらない、と言ったりする。
また、
「お客をカボチャか、ジャガイモだと思え」という言い伝えもある。
大きさからいえば、
沢庵石や西瓜でも良さそうなものだが、
なぜか、
カボチャかジャガイモという事になっている。
その言い伝え、
どうも科学的側面から、
まるで根拠がないとも言えない結果が出たようだ。
19日のCNN News によると、アメリカの航空会社ボーイングは、
機内無線通信サービスの安全性を検証するための
ジャガイモを使った画期的な実験方法を確立したと出ていた。
読み進めてみると、
その実験、
ジャガイモを客の姿に形成し、座席にのせて
電子信号に対する反応を調べると、
極めて、人体の反応と似ているという実験結果が出た。
そんな人に対するおまじないに、
掌(てのひら)に指で「人」という字を書いて
それを呑むマネをするとあがらない、と言ったりする。
また、
「お客をカボチャか、ジャガイモだと思え」という言い伝えもある。
大きさからいえば、
沢庵石や西瓜でも良さそうなものだが、
なぜか、
カボチャかジャガイモという事になっている。
その言い伝え、
どうも科学的側面から、
まるで根拠がないとも言えない結果が出たようだ。
19日のCNN News によると、アメリカの航空会社ボーイングは、
機内無線通信サービスの安全性を検証するための
ジャガイモを使った画期的な実験方法を確立したと出ていた。
読み進めてみると、
その実験、
ジャガイモを客の姿に形成し、座席にのせて
電子信号に対する反応を調べると、
極めて、人体の反応と似ているという実験結果が出た。
2015年05月29日
カバンと言えば
明治後期から大正時代にかけての作家に
泉 鏡花(いずみ きょうか)がいる。
作風としては、
江戸文芸の影響をうけ、
怪奇趣味と特有のロマンティシズムで知られている。
古典的な文体のためDr. Reborn呃人、
現代人にとっては読みづらい作家でもあるが、
どうしてどうしてDr. Reborn呃人、
今でも売れているそうだ。
彼が、生まれ育った街である金沢の
花街を舞台にしたものが多いDr. Reborn呃人。
そのせいか、骨董品を鑑賞する如く、
読みふける人も多いという。
私生活でも変人ぶりを発揮するようなところも
多かったそうだ。
そのエピソードの一つを紹介すると、
「あるとき、彼が小説を書いていたところ、
漢字がわからなり、妻に訊ねると、
(よくある如く) 空中に、その字を書いて示すと、
しばらく経って、『その文字を早く消しなさい』と
真顔で怒るように言った」
という。
神聖な文字を残しておくと、
その文字が死んで、
祟りをもたらすという意味だったようだ。
そのような、神秘性の世界が彼にはあった。
鏡花の小説に、
『革鞄(かばん)の怪』という短編小説がある。
それは、
ある旅行者の男が旅館に持ってきた
床に置かれた革鞄の中から
夜になって人の声が聞こえてくる、、
というところからストーリーが展開される。
いかにも怪奇趣味的な書き出しだが、
カバンというものは、
何かしら不気味で神秘的な雰囲気を持つものらしい。
カバンと言えば、
ここしばらくの事件で、
オウム事件の特別手配容疑者だった高橋克也被告が、
逃走時に持っていたとされる大きなカバン。
広島で起きた小学生をカバンに詰めて監禁した事件など、
カバンに関連する事件が多かった。
カバンの不気味さを如実に示す事件のように思える。
鏡花が表現したように、
カバンというものには、神秘性が潜んでいそうだ。
泉 鏡花(いずみ きょうか)がいる。
作風としては、
江戸文芸の影響をうけ、
怪奇趣味と特有のロマンティシズムで知られている。
古典的な文体のためDr. Reborn呃人、
現代人にとっては読みづらい作家でもあるが、
どうしてどうしてDr. Reborn呃人、
今でも売れているそうだ。
彼が、生まれ育った街である金沢の
花街を舞台にしたものが多いDr. Reborn呃人。
そのせいか、骨董品を鑑賞する如く、
読みふける人も多いという。
私生活でも変人ぶりを発揮するようなところも
多かったそうだ。
そのエピソードの一つを紹介すると、
「あるとき、彼が小説を書いていたところ、
漢字がわからなり、妻に訊ねると、
(よくある如く) 空中に、その字を書いて示すと、
しばらく経って、『その文字を早く消しなさい』と
真顔で怒るように言った」
という。
神聖な文字を残しておくと、
その文字が死んで、
祟りをもたらすという意味だったようだ。
そのような、神秘性の世界が彼にはあった。
鏡花の小説に、
『革鞄(かばん)の怪』という短編小説がある。
それは、
ある旅行者の男が旅館に持ってきた
床に置かれた革鞄の中から
夜になって人の声が聞こえてくる、、
というところからストーリーが展開される。
いかにも怪奇趣味的な書き出しだが、
カバンというものは、
何かしら不気味で神秘的な雰囲気を持つものらしい。
カバンと言えば、
ここしばらくの事件で、
オウム事件の特別手配容疑者だった高橋克也被告が、
逃走時に持っていたとされる大きなカバン。
広島で起きた小学生をカバンに詰めて監禁した事件など、
カバンに関連する事件が多かった。
カバンの不気味さを如実に示す事件のように思える。
鏡花が表現したように、
カバンというものには、神秘性が潜んでいそうだ。
2015年05月28日
Nokia and Xiaomi ink patent and equipment deal
Nokia and Xiaomi ink patent and equipment deal, year after buying 1,500 patents from Microsoft, Xiaomi is digging into the global intellectual property pool once again. Nokia has announced that it has entered into a wide-ranging patent licensing and purchase deal with Xiaomi, the Chinese maker of smartphones, wearables and other hardware, which will also become a customer of Nokia’s for networking equipment
.
The deal covers three main areas: Nokia and Xiaomi have inked a cross licensing deal covering cellular standard essential patents; Xiaomi has acquired unspecified patents from Nokia; and Nokia will provide network equipment to Xiaomi and will collaborate on building IP transport solutions. The pair will also consider “further cooperation” in other areas Internet of Things, augmented and virtual reality and artificial intelligence.
“As a company seeking to deliver more exciting technological innovations to the world, we are excited at the opportunity to work more closely with Nokia in future,” said Lei Jun, chairman and CEO of Xiaomi, in a statement. “Xiaomi is committed to building sustainable, long-term partnerships with global technology leaders. Our collaboration with Nokia will enable us to tap on its leadership in building large, high performance networks and formidable strength in software and services, as we seek to create even more remarkable products and services that deliver the best user experience to our Mi fans worldwide.”
We’ve asked, and both Nokia and Xiaomi have declined to provide further detail on which patents Xiaomi has acquired, or any of the financial terms of the deal 收緊輪廓.
It’s also not clear how and if the Nokia patents are related to those Xiaomi purchased from Microsoft: if you recall, Microsoft and Nokia were once close partners, and then Microsoft acquired Nokia’s handset business, before eventually winding that disastrous venture down.
The news points to a couple of ongoing stories in the technology world. For starters, it’s a mark of how patents and the wielding of them continues to sway larger business movements in the industry.
In May, Nokia and Apple settled a long-running patent dispute that threatened to disrupt Nokia’s wearables business and more. The value of these deals is often not made public, but it is not negligible: documents once revealed that licensing deals between Samsung and Microsoft are worth $1 billion a year.
Another interesting theme in patent disputes lies in how they are used as leverage for bigger business deals.
In the case of Xiaomi and Nokia, Xiaomi will become a customer of Nokia’s for network equipment — specifically “network infrastructure equipment designed to deliver the high capacity, low power requirements expected by large web providers and datacenter operators” and “optical transport solutions for datacenter interconnect, IP Routing based on Nokia’s newly announced FP4 network processor, and a data center fabric solution
.”
Longer term, it also opens the door to further collaboration in other areas.
“Xiaomi is one of the world’s leading smartphone manufacturers and we are delighted to have reached an agreement with them,” said Rajeev Suri, President & CEO of Nokia, in a statement. “In addition to welcoming such a prominent global technology company to our family of patent licensees, we look forward to working together on a wide range of strategic projects.”
IoT, notably, has been a focus for both companies. Xiaomi says that its Mi IoT platform now has more than 60 million connected devices on it, with over 8 million daily active connected devices.
Xiaomi was once a much-watched juggernaut in the world of mobile phones, with many wondering if it had what it took to unseat those who have been at the top of the smartphone game for years now, namely Samsung and Apple.
The fact that Xiaomi is in 30 countries but has never launched direct sales of handsets in the U.S. — focusing instead on accessories and so on, and selling actual devices in China, India and select other markets — has been a hindrance to that bigger potential. So it’s natural to wonder if deals like this could help pave the way for that kind of expansion.
“This is a really significant milestone that will take us further,” a spokesperson. “Sustainable and long term agreements with partners like Nokia lay the ground for global expansion.”
.
The deal covers three main areas: Nokia and Xiaomi have inked a cross licensing deal covering cellular standard essential patents; Xiaomi has acquired unspecified patents from Nokia; and Nokia will provide network equipment to Xiaomi and will collaborate on building IP transport solutions. The pair will also consider “further cooperation” in other areas Internet of Things, augmented and virtual reality and artificial intelligence.
“As a company seeking to deliver more exciting technological innovations to the world, we are excited at the opportunity to work more closely with Nokia in future,” said Lei Jun, chairman and CEO of Xiaomi, in a statement. “Xiaomi is committed to building sustainable, long-term partnerships with global technology leaders. Our collaboration with Nokia will enable us to tap on its leadership in building large, high performance networks and formidable strength in software and services, as we seek to create even more remarkable products and services that deliver the best user experience to our Mi fans worldwide.”
We’ve asked, and both Nokia and Xiaomi have declined to provide further detail on which patents Xiaomi has acquired, or any of the financial terms of the deal 收緊輪廓.
It’s also not clear how and if the Nokia patents are related to those Xiaomi purchased from Microsoft: if you recall, Microsoft and Nokia were once close partners, and then Microsoft acquired Nokia’s handset business, before eventually winding that disastrous venture down.
The news points to a couple of ongoing stories in the technology world. For starters, it’s a mark of how patents and the wielding of them continues to sway larger business movements in the industry.
In May, Nokia and Apple settled a long-running patent dispute that threatened to disrupt Nokia’s wearables business and more. The value of these deals is often not made public, but it is not negligible: documents once revealed that licensing deals between Samsung and Microsoft are worth $1 billion a year.
Another interesting theme in patent disputes lies in how they are used as leverage for bigger business deals.
In the case of Xiaomi and Nokia, Xiaomi will become a customer of Nokia’s for network equipment — specifically “network infrastructure equipment designed to deliver the high capacity, low power requirements expected by large web providers and datacenter operators” and “optical transport solutions for datacenter interconnect, IP Routing based on Nokia’s newly announced FP4 network processor, and a data center fabric solution
.”
Longer term, it also opens the door to further collaboration in other areas.
“Xiaomi is one of the world’s leading smartphone manufacturers and we are delighted to have reached an agreement with them,” said Rajeev Suri, President & CEO of Nokia, in a statement. “In addition to welcoming such a prominent global technology company to our family of patent licensees, we look forward to working together on a wide range of strategic projects.”
IoT, notably, has been a focus for both companies. Xiaomi says that its Mi IoT platform now has more than 60 million connected devices on it, with over 8 million daily active connected devices.
Xiaomi was once a much-watched juggernaut in the world of mobile phones, with many wondering if it had what it took to unseat those who have been at the top of the smartphone game for years now, namely Samsung and Apple.
The fact that Xiaomi is in 30 countries but has never launched direct sales of handsets in the U.S. — focusing instead on accessories and so on, and selling actual devices in China, India and select other markets — has been a hindrance to that bigger potential. So it’s natural to wonder if deals like this could help pave the way for that kind of expansion.
“This is a really significant milestone that will take us further,” a spokesperson. “Sustainable and long term agreements with partners like Nokia lay the ground for global expansion.”
2015年05月27日
イギリスの詩人ロバート
イギリスの詩人ロバート・ブリッジスは、
「あたかも、頭上の蒼穹(そうきゅう=空)から、その要石(かなめいし)が落ちたようだ」
という言葉をのこした。
それは1901年1月22日、
イギリスのヴィクトリア女王の逝去を聞いて、
その思いを表現した言葉だった。
ヴィクトリア女王は、18歳で即位し64年間公開大學 課程その地位にあり、
「光栄ある大英帝国」のシンボル的存在だった。
その間、産業革命を推進し、イギリスは、世界で最も輝いていた国であった。
その死去を境に翳りが見え始め、
まさに、空の要石が落ちてしまったような衰退が始まった。
とは言え、金融などイギリスの力は、未だに強いものがあり、
EU に対しても強気の姿勢が見えるこの頃でもある。
「蒼穹の要石(かなめいし)が落ちる」という表現は、
さすがに詩人と思わせるが、
これで、すぐに思い浮かべるのは、『杞憂』という言葉。
「中国古代の杞の人が、空が崩れ落ちてきはしないかと心配して
食事も喉を通らなくなった」という故事。
遠いアフリカで邦人が事件に巻き込まれたり、
尖閣諸島をめぐっての問題も発生している。
何につけても「杞憂」という言葉ですまないところがある。
杞憂と言えば、
何度かオフィスの前の交差点で、決まって苦しそうな顔をして、
十数分間あまり、
空を見上げている老人を眼にすることがあった。
空模様を見ているだけなのか、空の異変を感じているのか、
不安げな表情が、気になって仕方なかった。
わざわざ出向いていって『何事ですか?』と訊くには大袈裟(おおげさ)すぎると、
敢(あ)えて訊くのを躊躇(ためら)っていた。
あるとき、たまたま歩いている時に、その老人が
いかにも苦しそうに空を見上げているところに出くわした。
穏便に、
「空の観察ですか?」と訊いた。
老人は、向き直り、苦笑いを浮かべて、
「こうやって首を上に向けると、肩こりが和らぐんじゃ」
2015年05月26日
論ずることをせずに採決
愚かな人のことを称して「アンポンタン」ということがある。
この語源は、諸説渦巻いている。
一つは、「阿呆」のことを子供用語で「アッポ」と言い、
人をあらわす「タン」をつけて中環通渠、
「アンポンタン」呼ぶようになった説。
また、江戸市中に出回ったカサゴの一種の名前を「アンポンタン」と呼び、
その魚が、大きい割には、おいしくないということで、
「ウドの大木」と同様に意味で使われるようになったなどがある。
語源からいうと、今ひとつ説得力がない香港仔通渠。
そこで、もう一つあるのが中国語説佐敦通渠。
愚かな人を意味する中国語に「王八蛋」というのがある。
この発音が、「アンポンタン」の音に似ているところから、
聞き取った日本人がそのようにいうようになった説がある。
そう言えば、大きな予算を使いつつ、
日本の政治は、「ウドの大木」のような、
「決められない政治」と世界から言われたりする。
今、抱えている問題に対する議論をしたり、
どのような未来を描いていくかの争点を明確にして
質疑をするとかの姿勢も見えてこない。
そして、
論ずることをせずに採決。
我々が、ここ数年見せつけられてきたものは、
このワンパターン。
離反した行動をとっていると非難される人物も
手法は、ワンパターン。
議論は、沸き起こらない。
何も変わらない。
「アンポンタン」ばかり。
語源とされる中国語の『王八蛋』、
じっくり見ると、ワンパターンと読める。
おっ?
「アンポンタン」は、ワンパターン!
この語源は、諸説渦巻いている。
一つは、「阿呆」のことを子供用語で「アッポ」と言い、
人をあらわす「タン」をつけて中環通渠、
「アンポンタン」呼ぶようになった説。
また、江戸市中に出回ったカサゴの一種の名前を「アンポンタン」と呼び、
その魚が、大きい割には、おいしくないということで、
「ウドの大木」と同様に意味で使われるようになったなどがある。
語源からいうと、今ひとつ説得力がない香港仔通渠。
そこで、もう一つあるのが中国語説佐敦通渠。
愚かな人を意味する中国語に「王八蛋」というのがある。
この発音が、「アンポンタン」の音に似ているところから、
聞き取った日本人がそのようにいうようになった説がある。
そう言えば、大きな予算を使いつつ、
日本の政治は、「ウドの大木」のような、
「決められない政治」と世界から言われたりする。
今、抱えている問題に対する議論をしたり、
どのような未来を描いていくかの争点を明確にして
質疑をするとかの姿勢も見えてこない。
そして、
論ずることをせずに採決。
我々が、ここ数年見せつけられてきたものは、
このワンパターン。
離反した行動をとっていると非難される人物も
手法は、ワンパターン。
議論は、沸き起こらない。
何も変わらない。
「アンポンタン」ばかり。
語源とされる中国語の『王八蛋』、
じっくり見ると、ワンパターンと読める。
おっ?
「アンポンタン」は、ワンパターン!
2015年05月21日
調べてみると
『袖すり合うも他生の縁』
他生という表現がちょっと難しい。
簡単に言えば、『前世』ということになるので、上記のPretty renew 傳銷ことばの意味は、
「今、隣にいるこの人でさえ、何か前世で縁があった人なんだ」という解釈でいいかと思います。
英語表現でも"previous world" という表現で、慣用的に使うことから考えれば、
『他生』という仏教的な表現ですが、抵抗なく英語圏の人にも理解してもらえます。
小さな外国語スクール(私)は、外国語スクールを開いてより、21Pretty renew 傳銷が経ってしまいました。小さなままのスクールで「持ちこたえてきたことが嬉しくて今に至る」というところでしょうか>。
その中で、この『多生の縁』かな、と思えることがたくさん。
先日、チェコ語の講師Suzanaと話しをしていたときもPretty renew 傳銷、
1分1秒でも時間軸の歯車が違っていれば、この『小さな外国語スクール』との出会いはなかったと。
そういうものだと思います。
$BOOTS STRAP
チェコ語をやっているスクールということ自体が、ちょっと不思議な存在。
最近よくいわれる言葉に
『癒し系の人』という表現がある。
意味としては、安らぎを感じさせる人のことだという。
調べてみると、一般的に言われるようになったのは、平成12年(2000)頃からだそうだ。
事によると、都合のいい人過ぎて優柔不断になってしまう場合があります。
この『癒し』という文字、
ヤマイダレの中の文字『愈』の文字は、もともと「切る」を意味する言葉だと言う。
病気は、そのままで治るのではなく痛みを伴って「切る」という行為をすることによって治る。
『治癒行為』は、痛みを伴うということである。
『癒し系の人』は、『都合のいい人』になってはいけない。(ちょっと自戒でもある)
同様に、『縁』と言ったときに、すべての『縁』を大切にすることも重要だが、
見極めて「切る」という行動も必要だ。
これまでの半生を振り返ってみると、良縁の中で生きて来ることができたように思う。
吾知らず、なんとか「切ったり」しながら、その取捨選択をしてきたのだろうかと思ったりする。
チェコ語講師Suzanaが、小さな外国語スクールにいることは、
まさに『多生の縁』。
良縁に感謝といったところでしょうか?
ありがたい!
他生という表現がちょっと難しい。
簡単に言えば、『前世』ということになるので、上記のPretty renew 傳銷ことばの意味は、
「今、隣にいるこの人でさえ、何か前世で縁があった人なんだ」という解釈でいいかと思います。
英語表現でも"previous world" という表現で、慣用的に使うことから考えれば、
『他生』という仏教的な表現ですが、抵抗なく英語圏の人にも理解してもらえます。
小さな外国語スクール(私)は、外国語スクールを開いてより、21Pretty renew 傳銷が経ってしまいました。小さなままのスクールで「持ちこたえてきたことが嬉しくて今に至る」というところでしょうか>。
その中で、この『多生の縁』かな、と思えることがたくさん。
先日、チェコ語の講師Suzanaと話しをしていたときもPretty renew 傳銷、
1分1秒でも時間軸の歯車が違っていれば、この『小さな外国語スクール』との出会いはなかったと。
そういうものだと思います。
$BOOTS STRAP
チェコ語をやっているスクールということ自体が、ちょっと不思議な存在。
最近よくいわれる言葉に
『癒し系の人』という表現がある。
意味としては、安らぎを感じさせる人のことだという。
調べてみると、一般的に言われるようになったのは、平成12年(2000)頃からだそうだ。
事によると、都合のいい人過ぎて優柔不断になってしまう場合があります。
この『癒し』という文字、
ヤマイダレの中の文字『愈』の文字は、もともと「切る」を意味する言葉だと言う。
病気は、そのままで治るのではなく痛みを伴って「切る」という行為をすることによって治る。
『治癒行為』は、痛みを伴うということである。
『癒し系の人』は、『都合のいい人』になってはいけない。(ちょっと自戒でもある)
同様に、『縁』と言ったときに、すべての『縁』を大切にすることも重要だが、
見極めて「切る」という行動も必要だ。
これまでの半生を振り返ってみると、良縁の中で生きて来ることができたように思う。
吾知らず、なんとか「切ったり」しながら、その取捨選択をしてきたのだろうかと思ったりする。
チェコ語講師Suzanaが、小さな外国語スクールにいることは、
まさに『多生の縁』。
良縁に感謝といったところでしょうか?
ありがたい!
2015年05月18日
上から覗き込むと
下のレンズがフイルム撮影のためのレンズで、
上のレンズは、どのように映るかのモニターのためのレンズ。
上から覗き込むと、
カメラを向けている映像が、Invisalign隱適美磨(す)りガラスに映し出される。
まるで、光のすることを覗き見ているような、
ガラスに映る ”ぼんやり”の加減が何とも言えず魅力的だった。
オランダの画家フェルメールは、その原理と同じ筐体を覗いて、
数々の作品を完成させたという。
彼の作品に登場する人物に、何とも言えないリアル感があるのは、
そのせいだった?